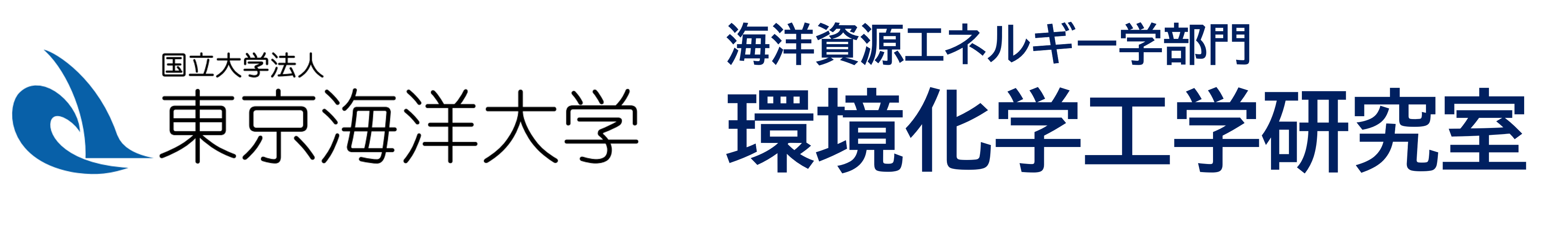第12回ZAIKEN Festa (2025.10.23)
第12回ZAIKEN Festaが早稲田大学・各務記念材料技術研究所(以下,材研)で開催されました。材研は多数の加工,表面分析機器(SEM, TEM, XPS等)を備えた都内でも有数の研究施設で(詳細),当研究室も共同研究契約により様々な分析技術でお世話になっています。今回,修士1年の中村碧さんと学部4年の佐々木直哉君がポスターセッションで発表しました。今回の発表で,加藤君が最優秀賞を受賞し,賞状と楯が授与されました。おめでとうございます!また,中村さんと同じフィールドを対象に共同研究を行っている牧田研究室・修士1年の伊藤裕基君は,最優秀賞を受賞しました。おめでとうございます!
第72回地球化学会年会 (2025.9.17-19)
第72回地球化学会年会が東北大学で開催されました。環境地球化学・放射化学セッションでは修士2年の加藤聖也君が「地球化学モデルを用いた坑廃水中のマンガン処理における炭酸塩生成メカニズムの速度論的考察 」というタイトルで口頭発表を行いました。また,修士1年の中村碧さんは工学や農学と地球化学の接点のセッションで「酸性坑廃水中のFe(II)酸化反応速度における鉄酸化細菌の影響および生成する鉄スラッジのヒ素除去特性」について発表しました。懇親会では仙台名物の牛タンや地酒を堪能しました。また,加藤聖也君は学生優秀賞を受賞しました。おめでとうございます!
資源・素材学会2025年秋季大会 (2025.9.2-4)
北海道大学で開催された資源・素材学会2025秋季大会に参加しました。ポスターセッションでは修士2年の加藤聖也君が「坑炭酸イオンを含む坑廃水の中和処理におけるCalcite生成とMn除去効率の関係」というタイトルで発表しました。また,同じフィールドを対象に共同研究を行っている牧田研究室・修士1年の伊藤裕基君が「伊達鉱山酸性坑廃水中の鉄酸化細菌が廃水処理に与える影響」のタイトルで発表を行いました。淵田先生は環境セッションで「酸性坑廃水の曝気処理における鉄処理効率に関係する化学条件の考察」,企画講演で「海洋性鉄酸化細菌を用いた銅鉱石の海水浮遊選鉱法」の2件の口頭発表を行いました。加藤聖也君,佐々木直哉君,伊藤裕基君は資源塾のOBOGセッションにも参加し,ポスター発表を行い非鉄金属資源企業関係者と交流を深めました。
第22回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会 (2025.8.8)
資源・素材学会・関東支部が主催する「資源・素材・環境」技術と研究の交流会 が東京大学本郷キャンパスで行われました。学生ポスターセッションでは修士2年の清水佑馬君が「高アルカリ度坑廃水の中和処理におけるCalcite生成のMn除去効率および生成神殿物への影響」,修士1年の中村碧さんが「伊達鉱山酸性坑廃水中の溶存鉄処理条件の検討および生成するスラッジのヒ素除去特性」,学部4年の佐々木直哉君が「異なる中和剤を用いた坑廃水処理における殿物生成量と有害元素除去効率の違いおよび経済性評価」というタイトルで発表を行いました。また,同じフィールドを対象に共同研究を行っている牧田研究室・修士1年の伊藤裕基君が「伊達鉱山酸性坑廃水中の鉄酸化細菌が廃水処理に与える影響」のタイトルで発表を行いました。学部4年生は研究を始めて半年という短い時間でしたが,実験や発表資料の作成を頑張りました。発表終了後には非鉄金属資源企業の説明会が行われ,業界や各企業が取り組む課題について学ぶことが出来ました。
Goldschmidt 2025 Conference (2025.7.6-11)
地球化学分野で最大規模の国際学会であるGoldschmidt 2025 Conferenceがチェコ・プラハで開催されました。ポスターセッションでは修士2年の加藤聖也君が「Mn removal mechanism from neutral pH mine water coexisting bicarbonate and calcium ions in active treatment」,修士2年の川崎麻未さんが「Investigation on arsenic dissolution behavior and its bearing minerals in seafloor massive sulfide ores」,淵田先生が「Microbial iron removal process by aeration and schwertmannite formation from acid mine drainage at the Date mine, Japan」というタイトルで発表を行いました。
環境資源工学会 第143回学術講演会 (2025.6.18)
環境資源工学会の第143回学術講演会が北海道大学・札幌キャンパスで開催されました。本学術講演会は「資源と情報/バイオテクノロジー」と題され,資源開発における機械学習の活用や微生物を用いた金属資源回収技術に関する話題について講演を聴講しました。学生ポスターセッションでは修士1年の中村碧さんが「伊達鉱山酸性坑廃水処理における水質の季節変化の影響および溶存鉄の選択的除去方法の検討 」というタイトルで発表を行いました。また,同じフィールドを対象に共同研究を行っている牧田研究室・修士1年の伊藤裕基君が「伊達鉱山酸性坑廃水中の鉄酸化細菌叢の季節変化および鉄除去プロセスに与える影響」のタイトルで発表を行いました。中村さんは優秀ポスター賞を受賞しました。おめでとうございます!
素材学会第50回奨励賞 (2025.3.13)
淵田先生が資源・素材学会第50回奨励賞を受賞しました。受賞タイトルは「坑廃水処理および鉱物分離技術の高度化を目的とした地球化学的研究」です。
第11回ZAIKEN Festa (2024.10.3)
第11回ZAIKEN Festaが早稲田大学・各務記念材料技術研究所(以下,材研)で開催されました。材研は多数の加工,表面分析機器(SEM, TEM, XPS, EPMA等)を備えた都内でも有数の研究施設で(詳細),当研究室も共同研究契約により様々な分析技術でお世話になっています。今回,修士1年の川崎麻未さんと修士1年の加藤聖也君が材研で測定したデータをポスターセッションで発表しました。今回の発表で,加藤君が最優秀賞を受賞し,賞状と楯が授与されました。おめでとうございます!
Curtin U and Waseda U Collaborative Symposium (2024.10.2-3)
循環バリューチェーンコンソーシアム・特別シンポジウムが早稲田大学で開催されました。このシンポジウムではエネルギー転換・重要鉱物・サーキュラーエコノミーに関する講演が行われました (詳細)。修士1年の加藤聖也君は「Kinetic Investigation of Sulfate and Carbonate ion inhibitions for Mn(II) removal during Mine Drainage treatment」というタイトルで,川崎麻未さんは「Experimental investigation of suitable disposal process for seafloor mining sulfide wastes using chemical reagents」というタイトルで口頭発表を行いました。また,淵田先生は「A novel flotation technique: pyrite depression using marine Fe(II)-oxidizing bacteria (MFeOB) in seawater flotation」について発表しました。
第71回地球化学会年会 (2024.9.18-20)
第71回地球化学会年会が金沢大学で開催されました。新たな試みとして開催された工学や農学と地球化学の融合セッションでは修士2年の清水佑馬君が「海洋性鉄酸化細菌の酸化・吸着ポテンシャルに基づく黄鉄鉱および黄銅鉱の浮遊選鉱効果の評価」というタイトルで口頭発表を行いました。また,淵田先生は環境地球化学セッションで「坑廃水処理におけるマンガン沈殿除去の地球化学」について発表しました。
資源・素材学会2024年秋季大会 (2024.9.10-12)
秋田大学で開催された資源・素材学会2024秋季大会に参加しました(詳細)。環境セッションでは修士1年の加藤聖也君が「坑廃水処理における硫酸および炭酸イオンのMn沈殿速度への影響」というタイトルで口頭発表を行いました。また,淵田先生は2019年度より実施している学会長期プロジェクトテーマ「海水浮遊選鉱における海洋鉄酸化細菌を用いた黄鉄鉱の浮遊抑制技術の検討」のフォローアップについて発表しました。加藤聖也君は資源塾のOBOGセッションにも参加し,ポスター発表を行い非鉄金属資源企業関係者と交流を深めました。
The 63rd Annual Conference of Metallurgists (2024.8.19-22)
カナダのHalifax Convention Centerで開催されたConference of Metallurgists (COM) に参加しました。今回は,バイオリーチングなど微生物を用いた鉱物資源処理をテーマに扱うInternational Biohydrometallurgy Symposium (IBS) も同時に開催され,同シンポジウムでは,修士2年の清水佑馬君が「Suitable Cultivating Conditions of Marine Fe-Oxidizing Bacteria for Pyrite Depression in Seawater Flotation System」というタイトルで,口頭発表を行いました (大変頑張りました)。また,修士1年の川崎麻未さんは「Kinetic evaluation of suitable immobilization process of heavy metals in seafloor massive sulfide for seafloor disposal of low-grade ore」というタイトルでポスター発表を行いました。長時間の移動で疲れもありましたが,国際学会に対面参加でき貴重な経験になりました。
第21回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会 (2024.8.8)
資源・素材学会・関東支部が主催する「資源・素材・環境」技術と研究の交流会が千葉工業大学・津田沼キャンパスで行われました。学生ポスターセッションでは修士1年の加藤聖也君が「地球化学モデルを用いた炭酸イオンを含むMn負荷坑廃水の最適処理法の検討」,同じく修士1年の川崎麻未さんが「海底熱水廃鉱石中の亜鉛およびヒ素の溶出特性および溶出抑制処理の検討」,学部4年の中村碧さんが「生物地球化学調査に基づく伊達鉱山坑廃水の中和処理条件の検討」というタイトルで発表を行いました。学部4年生は研究を始めて半年という短い時間でしたが,実験や発表資料の作成を頑張りました。
環境資源工学会 第142回学術講演会 (2024.6.14)
環境資源工学会の第142回学術講演会が九州大学・椎木講堂で開催されました。本学術講演会は「海底熱水鉱床研究開発の最前線」と題され,成因・探査・選鉱・環境・法制度など多岐にわたる話題について7名の方々の講演を聴講しました(詳細)。そのなかで,淵田先生は「鉱物溶解特性を踏まえた海底熱水鉱床開発で生じる廃棄物管理に関する予察的研究」というタイトルで,鉱床開発で発生する廃棄物の減容化を見据えた研究例について紹介しました。学生ポスターセッションでは修士1年の川崎麻未さんが「炭酸塩生成による海底熱水廃鉱石からのZn溶出抑制処理条件の検討」,同学年の加藤聖也君が「炭酸イオンを含む坑廃水の凝集沈殿処理におけるMn(II)酸化反応機構の速度論的考察」というタイトルで発表を行いました。また,共同研究を行っている神奈川工科大学・修士2年の三浦響さんが「海水浮遊選鉱における海洋性鉄酸化細菌の利用 および黄鉄鉱親水化機構の解明」のタイトルで発表し,優秀ポスター賞を受賞しました。おめでとうございます!
第70回地球化学会年会 (2023.9.21-24)
第70回地球化学会年会が本学で開催されました。久々の対面開催(一部オンライン配信あり)ということもあり,多くの方にご参加いただきました。「地球化学の融合セッション」では,淵田先生が「地球化学計算コードを活用した坑廃水中のマンガンなど重金属処理シミュレーション」というタイトルで講演しました。2日目には大学会館にて懇親会が実施され,大きな近大マグロの解体ショーが行われました(マグロのお寿司美味しかったです!!)。最終日には,「海洋の未来を拓くために~持続可能な社会の実現に向けた海洋利用~」というタイトルで市民講演会が実施され,4名の講師の先生方にご講演頂きました。さらに,3校の高校から研究発表が行われ,その後のパネルディスカッションでは,未来の資源やエネルギーに関して熱い議論が交わされました。
資源・素材学会2023年秋季大会 (2023.9.12-15)
愛媛大学で開催された資源・素材学会2023秋季大会に参加しました(詳細)。鉱物処理/リサイクル部門の学生ポスターセッションでは修士1年の清水佑馬君が「海洋性鉄酸化細菌を用いた海水浮遊選鉱における黄鉄鉱浮遊抑制効果の検証」というタイトルで,ショートプレゼンテーション,ポスター発表を行いました。また,淵田先生は2019年度より実施している学会長期プロジェクトテーマ「海洋の鉄酸化細菌を用いた有価硫化鉱物の海水浮遊選別法の開発」の総括を発表しました。学部4年の川崎麻未さんと加藤聖也君は8月に参加した資源塾が主催するセッションに参加し,非鉄金属資源企業のOBOGと交流を深めました。
第20回「資源・素材・環境」技術と研究の交流会 (2023.8.7)
資源・素材学会・関東支部が主催する「資源・素材・環境」技術と研究の交流会 がつくば国際会議場で行われました(詳細)。学生ポスターセッションでは修士1年の清水佑馬君が「海洋性鉄酸化細菌の黄鉄鉱浮遊抑制能力と海水浮選への利用可能性」,学部4年の川崎麻未さんが「熱水鉱石尾鉱から生じる有害元素不溶化処理方法の検討」,学部4年の加藤聖也君が「炭酸イオンを含む坑廃水中のマンガン除去機構の把握」というタイトルで発表を行いました。学部4年生は研究を始めて半年という短い時間でしたが,実験や発表資料の作成を頑張りました。発表終了後には非鉄金属資源企業の説明会が行われ,業界や各企業が取り組む課題について学ぶことが出来ました。また,最後に優秀ポスター発表賞の発表が行われ,見事修士1年清水君が選ばれました(詳細)。おめでとうございます!
環境資源工学会・第141回学術講演 (2023.8.3)
第141回学術講演会『-湿式法による貴金属の分離・回収技術に関する最近の動向-』が関西大学で開催されました(詳細)。学生ポスターセッションでは,修士1年の清水佑馬君が「海水浮選における海洋性鉄酸化細菌の増殖段階と黄鉄鉱への菌体吸着に関する考察」というタイトルで発表を行いました。初めての学会発表ということで大変緊張したと思いますが,多くの企業関係者や研究者から有益なコメントを頂き,良い経験になったと思います。
清水君のポスター発表の様子です